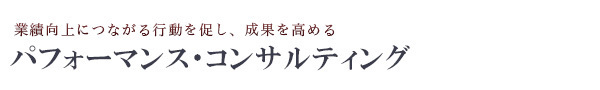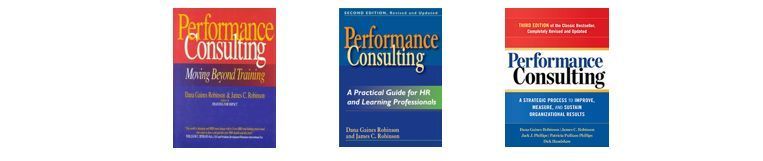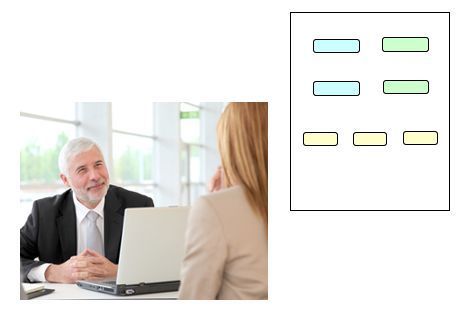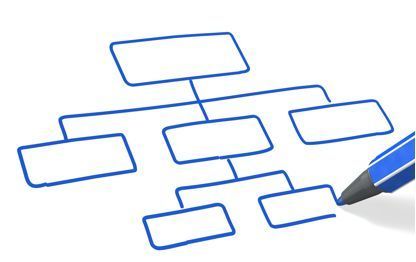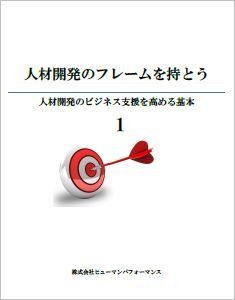『パフォーマンス・コンサルティングⅡ』の翻訳を終えて
10.07.28
ここでは、『パフォーマンス・コンサルティングⅡ』を解説します。
目次
1. 初版との違い
2. 日本語版によせて
お待たせしました。ついに、Performance Consulting second edition(2008)の翻訳、邦題『パフォーマンス・コンサルティングⅡ』2010年が出版されます。
本書を読む最大のメリットは、人事・人材開発の施策を通じて「事業の業績向上に貢献する」具体的な仕事の進め方がわかる、ということに尽きます。従来の人事・人材開発の考え方やアプローチをどのように変えればよいのか、具体的なイメージがきっと湧いてくるはずです。
初版の翻訳は「読む覚悟が必要」「途中疲れた」と知人に言われましたので、第二版の翻訳では「読みやすさ」を重視しました。力不足ではありますが、文語調・直訳調は避け、できるだけ和語を遣い、自然な日本語になるようにしました。この方針を守るために、出版社と少しストレスの高いやりとりをするという副産物もありました。



初版との違い
「人材開発の施策を通じて業績貢献をする」というコンセプトは初版と同じです。しかし、HRも視野に入っていたり、最新のモデルやツールを紹介されたりするなど、多くの点で進化し、初版とはまるで違う内容になっています。本書の軸足はHRと人材開発部門の両方にあり、初版以降に出たMoving from Training to Performance (1998)、Zap The GAPS!(2002)、Strategic Business Partner (2005)の3冊の本のエッセンスが統合されています。
翻訳しながら気づいたのですが、初版と同じ文章が見られるのはほとんどありませんでした。わずかに似た表現があったのは、第4章のアンケートの設計、第5章のデータ報告の仕方、第6章の契約などを説明している文章のほんの一部だけです。
初版との主な違いとしては、以下のようなことがあげられます。
- パフォーマンス・コンサルティングのプロジェクトの立ち上げから効果測定までの全体のプロセスを明示しながら解説している
- HRと学習部門の両方で活用できるコンセプトとして整理し直した
- パフォーマンス現状分析で活用するモデルやツールが進化し、洗練され、初版になかったツールも追加された
- 用語定義が明確になり、概念がわかりやすくなった
- 米国以外のことも含め、最新の事例を紹介し、理解を促進する演習もすべて刷新された
パフォーマンス・コンサルティング-基礎知識
| 初版 1995年 | 第2版 2008年 |
用語の定義 | パフォーマンス・コンサルティングの明確な定義がなかった 同義の言い換えが不明 | パフォーマンス・コンサルティングを明確に定義している 同義の用語も整理 |
HR・学習部門の業務の捉え方 | なかった | 戦略レベル、戦術レベル、事務処理レベル |
パフォーマンス・コンサルタントの役割 | 第1~2章で必要性と主な役割を解説 | 章立てした記述はない。全体の中で解説 |
ニーズの捉え方 | 4つのニーズ | ニーズの階層構造 |
現状分析ツール | パフォーマンス相互関係マップ | GAPS! マップ |
原因分析モデル | なかった | The Gap Zapper |
ソリューションの選択 | なかった | 基本的なガイドラインを示した |
クライアントへの対応 | 明確にはなかった | ACTモデル |
インタビューをするときのロジック | Should-Is-Cause | GAPS!ロジック |
詳しくはパフォーマンス・コンサルティングの現在
本書の特徴をあげれば、下記のようになります。
- パフォーマンス・コンサルティングを実践するためのモデルやツールについて、実際に活用するイメージが湧くように解説されている
- テキストらしく図表が67ほどあり、読後に手引きとして使えるものが多い
- 各章の理解が深まるように8つの事例、15の演習がある
- パフォーマンス現状分析がスピーディーにできるように、ショートカットするためのコツを示している
初版の読者は、おそらくパフォーマンス・コンサルティングの全体像がわかりやすくなったと感じられると思います。また、本書で初めて「フォーマンス・コンサルティング」にふれる方には、これまで疑問に思っていたことを解消するヒントがたくさん見つかると思います。
日本語版によせて
パフォーマンス・コンサルティングの背景には、何があるのだろう?
もうずいぶん前のことですが、そんな疑問を持ちながら、ロビンソン両氏がPerformance Consulting (1995)、Moving from Training to Performance (1998)であげていた参考文献をあたっていきました。英語はできませんが、とりあえず「当たって砕けろ」で、Handbook of HPT (1992), J. Hale (1998), G. Rummler (1995), T. Gilbert (1978), M. Broad (1992) などを少しずつ読み進めました。といっても、どこまで理解できたのか、はなはだ心もとないのですが。
そして、2000年の晩秋、ふたりの処女作、Training for Impact(1989)を読んだときのことです。パフォーマンス・コンサルティングの原点が少し見えたような気がしました。というのは、パフォーマンス・コンサルティングで紹介しているモデルの原形があちらこちらにあったからです。そして、Training for Impactというタイトルどおり、パフォーマンス・コンサルティングは「どうすれば研修を通じて業績の向上に貢献ができるか?」という素朴な問題意識から始まっていると思いました。
今回、『パフォーマンス・コンサルティングⅡ』の「日本語版によせて」を著者に依頼するにあたり、この仮説をぶつけてみました。「パフォーマンス・コンサルティングに取り組むようになったきっかけやこの分野を探究してきた動機についてふれてほしい」とお願いしたのです。
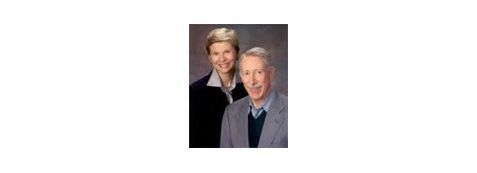
この「日本語版によせて」を読んでいただくとわかると思いますが、著者のロビンソン夫妻は、ふたりとも研修ファシリテーターの実務経験があります。ちなみに、Training for Impact(1989)によると、デイナ・ロビンソン氏はフィラデルフィア銀行、ジム・ロビンソン氏はAgway社で人材開発の実務を行っていたようです。その当時、ふたりはせっかく研修を実施しても実務で活かされなければ意味がないとすぐに気づいたそうです。つまり、パフォーマンス・コンサルティングが生まれた背景には、多くの人事・人材開発スタッフと共通の悩みがあったわけです。
パフォーマンス・コンサルティングは決して遠い世界のものではなく、我々に身近なところから始まっています。書名に「コンサルティング」と入っていますが、本書は人事・人材開発スタッフ向けの本です。ぜひ本書を読み、同僚と議論していただければと思います。
この本の出版で一区切りがつきましたので、今後は各企業の人事・人材開発スタッフ向けにパフォーマンス・コンサルティングを学ぶワークショップを開き、ご理解を深めていただく場を用意するつもりです。
近い将来、パフォーマンス・コンサルティングに関心のある人事・人材開発スタッフの方と実践研究会のようなことができればと考えています。率直なご意見・ご感想、そして、ご連絡をお待ちしています。
関連する記事
パフォーマンスコンサルティングとは-基礎知識
パフォーマンス・コンサルティング 1995~2025
事業・人材開発の効果的なニーズの把握と整理にはコツがあります
パフォーマンス・コンサルティングⅡ
事業成果・研修効果にこだわる人事・人材開発スタッフに、おすすめの一冊です。ビジネスと人材開発の連動を高めるための具体的なコツを整理した本です。
- 経営幹部から事業の観点で人材開発ニーズを聞きだす質問例
- 多くのニーズを構造的にまとめるツール
- 従業員のパフォーマンスが低いときの原因と対処例
- 経営幹部の戦略実行を支援した多くの事例等
人材開発の上流で役立つ情報が満載です。
コラム:パフォーマンス・コンサルティング30年の軌跡
ヒューマンパフォーマンスはパフォーマンス・コンサルティングを実践します。
人にかかわる施策、人材開発と事業戦略の連動性を高め、業績向上に貢献することがテーマです。研修効果で悩んだことがある方には有効なフレームワークです。人材開発のあり方や研修の見直しを検討されている人材開発担当の方におすすめです。
お気軽にお問い合わせください。
代表者プロフィール

鹿野 尚登 (しかの ひさと)
1998年にパフォーマンス・コンサルティングに出会い、25年以上になります。
パフォーマンス・コンサルティングは、日本企業の人事・人材開発のみなさまに必ずお役に立つと確信しています。
代表者プロフィール
代表ごあいさつはこちら